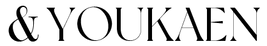梅の花言葉を詳しく解説!意味や由来とは

梅の花言葉を詳しく解説!意味や由来とは
厳しい寒さが残る中、どの花よりも先に咲き誇り、凛とした香りで春の訪れを告げる「梅の花」。
その清らかな姿から「高潔」「忍耐」といった力強い花言葉を持つ梅ですが、その花言葉がどのような背景から生まれたのか、その深い由来をご存知ですか?
この記事を読めば、「梅の花言葉」の本当の意味はもちろん、日本の歴史や文化(「松竹梅」や「菅原道真公」の伝説)と、梅がいかに深く結びついてきたのか、そのすべてがわかります。
&YOUKAENのフローリストが、梅の奥深い魅力を徹底解説!ぜひ最後までご覧ください。
梅の花の基本情報を押さえよう

まずは、梅がどのような植物なのか、基本的な情報を押さえておきましょう。
梅ってどんな植物?
| 植物名 | 梅 |
| 学名 |
Prunus mume |
| 科名 | バラ科 |
| 属名 | サクラ属 |
| 原産地 | 中国中南部 |
梅は、バラ科サクラ属の落葉高木です。実は、桃(もも)や桜(さくら)、杏(あんず)とは非常に近い親戚関係にあたります。
植物分類学上は、特に桃や杏に近い仲間とされています。
観賞用の「花梅(はなうめ)」と、実を採る「実梅(みうめ)」に大別されます。
梅の名前の由来は?
その名前の由来には諸説ありますが、中国での「梅(Mei、マイ)」の発音(呉音の「メ」)が日本に伝わり、「ウメ」に転じたという説が最も有力です。
他にも、蕾が「熟む(うむ)」から転じた説や、実を薬用に燻製にした「燻(う)べ」から来た説などがあります。
梅は英語でなんと言う?
一般的には「Plum blossom(プラム・ブロッサム)」と呼ばれることが多いです。
ただし、欧米でいう「Plum(プラム)」は主に「スモモ(西洋すもも)」を指すため、植物学的には「Japanese apricot(ジャパニーズ・アプリコット=日本の杏)」と呼ばれることもあり、正確に区別されています。
梅の花言葉は?

それでは、「梅の花言葉」について詳しく見ていきましょう。
梅の花言葉の多くは、その「咲き方」と、ある「歴史的な伝説」に深く由来しています。
「高潔」「忍耐」「上品」
これらの花言葉は、梅の咲き誇る姿そのものに由来します。
まだ雪が残り、他の花が固くつぼみを閉じている厳しい寒さの中、梅はどの花よりも先に、凛とした気品ある香りと共に花を咲かせます。
その姿が、厳しい状況にも屈しない「忍耐力」と、世俗に染まらない「高潔さ」、そして清らかな「上品」さを象徴しているとされました。
「忠実」
梅の花言葉の中で、ひときわ異彩を放つのが「忠実」です。
この花言葉の由来は、平安時代の偉大な学者であり政治家であった「菅原道真(すがわらのみちざね)」公と、彼が愛した梅の木の有名な伝説にあります。
道真公は、策略によって京都から遠い太宰府(現在の福岡県)へ左遷されることになりました。京都の邸宅を離れる際、日頃からこよなく愛でていた梅の木に向かい、こう詠みました。
「東風(こち)吹かば 匂ひおこせよ 梅の花 主(あるじ)なしとて 春を忘るな」
(春風が吹いたら、香りを私のもとまで届けておくれ、梅の花よ。主人がいなくなっても、春を忘れて咲くのを忘れてはならないよ)
主君を慕う梅の木は、道真公への「忠実」な想いから、なんと一夜にして京都から太宰府の道真公のもとまで飛んでいったとされています。
これが有名な「飛梅(とびうめ)伝説」であり、「忠実」という花言葉の由来となりました。
色別の花言葉は?
梅は花の色によっても、少しずつ異なる花言葉を持っています。
・紅梅(赤・ピンク): 「優美」「あでやかさ」
・白梅: 「気品」「純潔」「澄んだ心」
白梅は「高潔」「忍耐」のイメージがより強く、紅梅は華やかさや優雅さが表現されています。
梅は縁起の良いお花

梅は、その美しさだけでなく、日本や中国において非常に縁起の良い「吉祥花(きっしょうか)」とされています。
「松竹梅」の一つ
おめでたいものの象徴として使われる「松竹梅(しょうちくばい)」。これは、中国の「歳寒三友(さいかんのさんゆう)」という言葉に由来します。
「歳寒三友」とは、寒い冬(歳寒)にも変わらぬ姿を保つ3つの友、すなわち「松・竹・梅」のこと。
・松:厳寒でも緑を保つ「不老長寿」
・竹:雪にも折れずまっすぐ伸びる「繁栄」
・梅: いち早く花を咲かせる「生命力・希望」
梅は「厳寒の中で春を告げる、希望の象徴」として縁起物とされているのです。
中国では「五福」を表す吉祥花
梅の5枚の花びらは、中国で縁起が良いとされる「五福(ごふく)」を表しているとも言われています。
五福とは、「長寿」「富」「健康」「(人徳を積む)徳」「天命(天寿を全うすること)」の5つの幸福。梅は、まさに「幸福を呼ぶ花」なのです。
梅の歴史について

梅がいかに日本文化に深く根付いてきたか、その歴史をたどってみましょう。
紀元前から中国では親しまれていた
梅の原産地は中国とされ、紀元前から観賞用としてだけでなく、その実は「烏梅(うばい)」と呼ばれる漢方薬や、燻製にした保存食(梅干しの原型)として、人々の生活に密着していたようです。
(参考元:MDPI「Meizi-Consuming Culture That Fostered the Sustainable Use of Plum Resources in Dali of China: An Ethnobotanical Study」)
奈良時代に日本に伝来
奈良時代、遣唐使などによって薬や観賞用の植物として日本に持ち込まれたそうです。
ここで非常に興味深いのが、『万葉集』に詠まれた花の数です。実は、桜の歌が約40首なのに対し、梅の歌は約120首も詠まれています。
奈良時代において、「花といえば梅」であったことがわかります。
(参考元:国立国会図書館サーチ「初春の梅」)
平安貴族文化と梅
平安時代に入ると、貴族たちは梅の香りを愛し、邸宅に植えて愛でたそうです。
そして、先ほどの「菅原道真公」の飛梅伝説が生まれます。
(その後、国風文化が発達するにつれ、日本の野山に咲く「桜」へと人気が移っていきました…という通説があります)
(参考元:国交省「Plum Trees of Dazaifu」)
鎌倉・室町にはお寺の庭木に
禅宗の文化と共に、梅は水墨画の題材としても好まれ、その「忍耐」「高潔」という精神性が禅の教えと重なり、多くの寺院に植えられたとされます。
(参考元:メトロポリタン美術館「Plum Blossoms」)
(参考元:相国寺・金閣・銀閣 宝物展-梅の余薫 / 相国寺の歴史と寺宝)
江戸時代に園芸文化が爆発!梅が広がる
江戸時代に入ると空前の園芸ブームが起こり、多くの観賞用の「花梅」が作られました。
「梅見(うめみ)」が庶民の楽しみとして定着し、湯島天神や亀戸天神といった梅の名所は、多くの人々で賑わいました。
(参考元:Tokyo Museum Collection「江戸名所 亀戸梅屋舗」)
(参考元:Wikipedia「Hanami」)
現代では文化と信仰の象徴に
菅原道真公が「学問の神様(天神様)」として祀られていることから、梅は「合格祈願」の象徴ともなっています。
全国の天満宮(天神様)の神紋は「梅紋」であり、受験シーズンになると、梅の花が「厳しい冬を耐えて咲く」姿が、努力を重ねる受験生の姿と重なり、多くの人々の心の支えとなっています。
(参考元:太宰府天満宮)
梅の心をお部屋に。&YOUKAENが提案する春のしつらえ

梅の花言葉やその奥深い歴史を知り、その「厳しい寒さの中で咲く高潔さ」や、「春を告げる希望」の姿に、心を惹かれた方も多いのではないでしょうか。
&YOUKAENでは、梅の枝そのもののお取り扱いは現在ございませんが、その梅の心が通うような、春の訪れを告げる美しい花々を多数ご用意しています。
梅が咲き始めると、まるでその香りに誘われるように、他の花々も一斉に目を覚まします。
例えば、凛とした姿で希望を感じさせるチューリップ、幾重にも花びらが重なり、豊かさを感じさせるラナンキュラス。
これらもまた、梅と同じように冬の終わりを彩り、私たちに春の喜びを届けてくれる花々です。
梅の「忍耐」と「希望」の精神に思いを馳せながら、&YOUKAENがご提案する春のフラワーギフトで、お部屋に新しい季節を迎えてみませんか?
シャビーシックピンク Lサイズ 桜と春いっぱいのアレンジメント
¥15,400-
まとめ

梅の花の奥深い世界、お楽しみいただけたでしょうか。
・「梅の花言葉」は、「高潔」「忍耐」など、厳しい寒さの中で咲く凛とした姿に由来します。
・「忠実」という花言葉は、菅原道真公と梅の木との絆を描いた「飛梅伝説」という深い物語に由来しています。
・梅は「松竹梅」や「五福」の象徴であり、『万葉集』の時代から愛されてきた、非常に縁起が良く、歴史ある花です。
梅の花が持つ「希望」や「気品」を、ぜひ春の花々を通してお楽しみください。
&YOUKAENが、皆様の新しい季節の始まりを、心を込めてデザインした花々で彩るお手伝いをいたします。
◆修正履歴
2025年12月9日:参考文献・出典情報を追記。
Oct 30, 2025