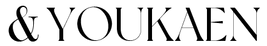藤袴(フジバカマ)の花言葉って何?歴史と香りの文化についても解説!

藤袴(フジバカマ)の花言葉って何?歴史と香りの文化についても解説!
秋の七草の一つ、藤袴(フジバカマ)。
淡いピンクや紫色の小さな花が集まって咲く、可憐で美しい花です。生け花やフラワーアレンジメントなどで使われることも多い花材でもあります。
可愛らしいお花ですが、そんな藤袴にはどんな花言葉があり、どんな歴史があるかご存知でしょうか?
この記事では、藤袴の花言葉から名前の由来、歴史、そして平安時代から続く香りの文化まで、藤袴の全てを徹底的に解説します。
藤袴の奥深い世界に触れ、その魅力に引き込まれてみませんか? きっと藤袴を飾ってみたくなるはずです。
藤袴(フジバカマ)の基本情報

まずは、藤袴がどんな花なのか、その基本情報から見ていきましょう。
藤袴(フジバカマ)ってどんな花?
| 植物名 | フジバカマ(藤袴) |
| 学名 |
Eupatorium japonicum |
| 科名 | キク科 |
| 属名 | ヒヨドリバナ属 |
| 原産地 | 中国 |
| 開花時期 | 8月から10月頃 |
藤袴はキク科の多年草です。
淡いピンクや紫色の小さな花が、房のように集まって咲くのが特徴です。
まっすぐと伸びた茎に涼しげな花を咲かせる姿が、秋の野山を美しく彩ります。
そして、一番の特徴は、乾燥させると桜餅のような甘く芳しい香りがすることです。
藤袴(フジバカマ)の名前の由来は?
藤袴という名前は、花の色と葉の形から名付けられました。
花が淡い藤色であること、そして葉が三裂し、袴をはいたような形に見えることから、「藤袴」と呼ばれるようになりました。
藤袴(フジバカマ)はどんな所に自生している?
藤袴は、元々は日本の河川の土手や原野に広く自生していました。
中国や朝鮮半島にも分布しています。
しかし、近年は開発や環境の変化により自生地が激減し、現在は準絶滅危惧種に指定されています。
各地で保全活動が行われている、貴重な花です。
藤袴(フジバカマ)の英名は?
藤袴には、特に広く知られた英名はありません。日本では有名なお花ですが、海外ではあまり知られていないのですね。
学術名としては「Eupatorium fortunei」が使われますが、「Boneset」と呼ばれることもあります。
藤袴(フジバカマ)の花言葉は?

藤袴の花言葉は、その可憐な姿や、歴史に基づく文化的な背景から生まれました。
1. 「優しい思い出」
藤袴を乾燥させると、桜餅のような甘く芳しい香りが漂います。
この香りは、遠い昔の懐かしい思い出を呼び起こさせる力を持っています。
平安時代の恋物語にも登場し、香りと共に思い出が蘇ることから、この花言葉が生まれたと言われています。
2. 「ためらい」
小さな花が密集して咲く姿は、まるで控えめに咲く人のようです。
派手さはなく、奥ゆかしい雰囲気を醸し出すその姿から、相手への想いをなかなか伝えられずにいる「ためらい」という花言葉が生まれました。
3. 「迷い」
『源氏物語』などの古典文学に登場する藤袴は、恋に揺れる心や、想いを伝えられずにいる登場人物の気持ちを象徴する花でもありました。
また、同じ歌の中で異なる意味合いを持つ花と合わせて詠まれることも多く、心の「迷い」を表す花として知られています。
藤袴は、その見た目だけでなく、香りや文学に彩られた歴史を持つことで、これらの繊細で美しい花言葉を持つようになったのです。
藤袴(フジバカマ)は秋の七草?

藤袴は「秋の七草」の一つです。ススキや桔梗と並び、秋の訪れを象徴する大切な花として、古くから日本人に愛されてきました。
山上憶良が『万葉集』で詠んだ歌に由来
秋の七草は、奈良時代の歌人、山上憶良が『万葉集』で詠んだ歌に由来します。
その歌は、「萩の花 尾花 葛花 撫子の花 女郎花 また藤袴 朝貌の花」というものです。
この歌に登場する植物が、現代に伝わる秋の七草となりました。藤袴は、この歌の中で明確に詠まれています。
春の七草と秋の七草の役割の違い
春の七草が、七草粥にして「食用」として楽しむのに対し、秋の七草は「観賞用」です。
藤袴も、その可憐な姿や、乾燥させると漂う甘い香りで、人々に秋の風情を感じさせる役割を担ってきました。
秋の七草をすべて集めて飾ると、まるで秋の野山を部屋に持ち込んだような、豊かな季節感を楽しめます。
藤袴(フジバカマ)の歴史について

藤袴は、単なる秋の七草の一つというだけでなく、その香りと美しさで日本の歴史を彩ってきました。
薬草としての歴史
藤袴の原産地は中国とされ、日本にはかなり古い時代に渡来したと考えられています。
当時、藤袴は、香りの良い植物としてだけでなく、解熱や利尿作用がある薬草としても重宝されていました。
病を癒す力を持つ植物として、大陸からもたらされたのでしょう。
(参考元:一般社団法人 奈良県薬剤師会「フジバカマ」)
奈良時代には万葉集に登場
藤袴の歴史が明確になるのは、奈良時代に編纂された『万葉集』です。
歌人の山上憶良が詠んだ「秋の七草」の歌に登場します。万葉集で藤袴を詠んだ歌は一首しかありませんが、この頃から、藤袴は日本の人々に広く親しまれるようになりました。
和歌の題材としても多く詠まれ、その可憐な姿や香りは、貴族たちの風流な遊びに欠かせないものでした。
(参考元:かぎけん花図鑑「万葉集と藤袴」)
現在では準絶滅危惧種へ…
明治以降、都市化や河川の整備が進むにつれて、藤袴の自生地は激減しました。
かつては野山で当たり前に見られた藤袴も、今では環境省のレッドリストで「準絶滅危惧種」に指定されるほど、貴重な存在となっています。
しかし、近年は、各地で保全活動や「藤袴まつり(京都市など)」が行われ、藤袴を守り、次の世代に伝えていこうとする動きが活発になっています。
(参考元:一般社団法人 奈良県薬剤師会「フジバカマ」)
平安時代では「香り」を楽しむための植物だった

藤袴が持つ香りは、平安貴族の文化にとって欠かせないものでした。
平安貴族と「香り」の価値観
平安時代の貴族は、単なる見た目の美しさだけでなく、「香り」を非常に重視していました。
香りは、その人の品格や教養を表すものと考えられていたのです。
沐浴や香湯(こうとう)に
藤袴を入れたお湯で沐浴する「香湯」は、貴族の身だしなみの一つでした。
体から良い香りを漂わせることで、自身の美意識を高めていたのだとされています。
宴や贈答での演出に
宴会の際、藤袴を焚いて部屋に香りを満たす、あるいは贈り物に添えて贈るなど、様々な演出に使われていました。
香りを通して、季節を感じさせたり、想いを伝えたりしていた、風流な文化があったのです。
実際に藤袴(フジバカマ)ってどんな香り?
生花の状態では、実はほとんど香りがしません。
しかし、乾燥させると「クマリン」という成分が発生し、桜餅やバニラのような甘く芳しい香りになるのです。
&YOUKAENでは秋の花を使用した花束を販売中!

&YOUKAENでは秋が旬の花束を販売中です。
この季節だけにしか出回らない旬のお花を使用して、おしゃれに仕上げています。
フローリストが市場で買い付けた旬の花を、一本一本品質を確かめて束ねていきます。
誕生日のプレゼントや結婚記念日のプレゼントにおすすめ。ぜひ大切な方にプレゼントしてあげてくださいね。
秋の花を使ったおしゃれな花束
秋のお花を使った 期間限定・洋風の花束 「kurenai」
¥8,800-
まとめ

藤袴は、「優しい思い出」という花言葉を持つ、奥ゆかしい花です。
秋の七草の一つとして、そして香りを楽しむ文化の象徴として、古くから日本人に愛されてきました。
藤袴を飾ることで、見た目だけでなく、香りからも秋を感じられることでしょう。
&YOUKAENでは秋が旬のお花をお楽しみいただけるように、花束やフラワーアレンジメントを多数ご用意しております。
ご自宅用はもちろんのこと、誕生日や結婚記念日などのプレゼントにもおすすめです。
大切な方への贈り物に、ご自宅のインテリアに、秋のお花を選んでみませんか?
専門フローリストが、皆さまのお花選びを心を込めてサポートさせていただきます。
Aug 11, 2025