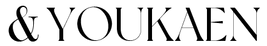萩の花言葉は?歴史や豆知識についても解説!

萩の花言葉は?歴史や豆知識についても解説!
秋の七草の一つ、萩(ハギ)。
細い枝をしなやかに曲げ、風に揺れる姿は、古くから日本人の心を捉えてきました。
萩はとっても優雅な花。お花に詳しくない方も、詳しい方もファンの多いお花です。そんな萩には、どんな花言葉や歴史があるかご存知でしょうか?
この記事では、萩の花言葉から名前の由来、歴史、そして意外な豆知識まで、萩の全てを徹底的に解説します。
萩の奥深い世界に触れ、その魅力に引き込まれてみませんか?
萩の花の基本情報

まずは、萩がどんな花なのか、その基本情報から見ていきましょう。
萩の花の特徴は?
| 植物名 | 萩(はぎ) |
| 学名 |
Lespedeza |
| 科名 | マメ科 |
| 属名 | ハギ属 |
| 原産地 | 東アジア |
| 開花時期 | 7月から9月 |
萩はマメ科の落葉低木です。
細い枝に、蝶のような形の小さな花がたくさん咲きます。色は紅色や紫色が一般的です。
枝がしなやかに垂れ下がる姿は、優雅で美しい印象を与えます。
秋の七草の中でも特に風情があり、多くの人々に愛されてきました。
同じマメ科と言うこともあり、見た目はスイートピーにちょっと似ているお花です。
萩の花の名前の由来は?
萩という名前は、毎年新芽が出てくる強い生命力から、「生え芽(はえき)」が転じて「ハギ」になったという説があります。
また、漢字で「萩」と書くことからもわかるように、「草冠に秋」で、秋を代表する草であることを示しています。
漢字で由来を知ることができて面白いですね。
萩の花が咲く季節は?
萩の開花時期は7月から10月頃です。
秋の七草に数えられているため、秋の花というイメージが強いですが、実際には夏から咲き始め、長い期間楽しめる花です。
萩の花はどんな所で咲く?
萩は、日本の山野や丘陵、河原など、日当たりの良い場所に広く自生しています。
自然の中に美しく咲く姿は、日本人の心を昔から癒してきました。
萩の花は英語でなんと言うの?その由来は?
萩の英名は「Bush Clover」です。「Bush」は「低木」を、「Clover」は「マメ科の植物」を意味し、萩の特徴を表しています。
また、「Japanese Clover」と呼ばれることもあります。
萩の花言葉について

萩の花言葉は、その優雅な姿や、控えめな咲き方に由来するものが多くあります。
1.「思案」
風に揺れる枝の姿は、まるで何かを深く考えている人のように見えます。
うつむき加減に咲く花の姿も、この花言葉を連想させ、奥ゆかしい雰囲気を醸し出しています。
アンニュイな様子が秋の季節感にピッタリですね。
2.「内気」
控えめな花の咲き方や、そっとうつむく姿は、恥ずかしがり屋で内気な女性の印象と結びつきます。
「内気」という花言葉は、ハギの持つ、主張しすぎない美しさを表しています。
3.「柔らかな心」
細い枝がしなやかに曲がり、風に吹かれるたびに優しく揺れる姿は、柔軟で穏やかな心を持つさまを表現しています。
この花言葉は、ハギの持つ優しい雰囲気にぴったりの言葉です。
萩の花の歴史は?

萩は、日本の歴史や文化を語る上で欠かせない存在です。
最古の歌集「万葉集」に登場
ハギの歴史は、日本最古の歌集である『万葉集』にまでさかのぼります。
山上憶良が詠んだ「秋の七草」の歌に、ハギは一番最初に登場します。
『万葉集』の中で最も多く詠まれた花でもあり、その数は140首以上。
秋の野に咲くハギは、当時の人々の心を捉え、恋の切なさや別れの寂しさ、はかない心情を表現する花として愛されていました。
(参考元:アサヒネット「萩の花 和歌歳時期」)
枕草子にも登場!
平安時代になると、ハギは貴族文化の中でさらに重要な役割を果たします。
『枕草子』
清少納言の『枕草子』には、「萩の葉の裏返るまで吹き破る風」という一文があり、暴風雨の後の荒れた庭の光景が描かれています。
(参考元:フロンティア古典教室「枕草子『野分のまたの日こそ』現代語訳」)
家紋にも使用された萩の花
萩はそのデザイン性から、家紋(紋章)として使われることがありました。
例えば九枚萩紋や「抱き萩」「束ね萩」「丸に九枚萩」など、いくつかのバリエーションがあります。
「萩紋」の由来や意味として、「再生」「子孫繁栄」「縁起の良い植物」として位置づけられていたそうです。萩はとても縁起の良い植物として、日本人に愛されてきました。
(参考元:家紋のいろは「萩紋(はぎ)について」)
名字や地名にも残る萩
萩は、日本の名字や地名に多く残されています。山口県の萩市は、かつてハギが自生する美しい場所であったことから名付けられました。
萩原(はぎわら)や萩野(はぎの)といった名字も、ハギが咲く場所に由来していることが多いです。
(参考元:萩市「萩市の概要」)
海外では土壌保全に使用された歴史も
海外では、日本とは少し異なる目的でハギが利用されてきました。
ハギの一種であるレソペデザ(Lespedeza)が、アメリカなどで牧草や痩せた土地の土壌を豊かにする目的で導入された歴史があります。
しかし、一部の地域では繁殖力が強すぎて在来種を駆逐してしまうため、現在では侵略的外来種として扱われ、その駆除が進められている場所もあります。
(参考元:US Forest Service「Lespedeza bicolor」)
(参考元: IUCN「Global Invasive Species Database:Lespedeza cuneata」)
萩の花の豆知識

萩は、日本人に古くから愛されてきた花だけに、面白いエピソードや意外な一面をたくさん持っています。
知っていると、さらに萩が好きになること間違いなしです。
万葉集の登場回数はダントツ!
山上憶良が詠んだ「秋の七草」の中でも、萩は特別な存在でした。
日本最古の歌集である『万葉集』に登場する植物の中で、圧倒的に多く詠まれています。
その数、なんと140首以上!
当時の貴族や庶民にとって、秋の野に咲く萩は、恋の切なさやはかない心情を表現する上で欠かせない花だったことがわかります。
家紋にも使われた萩の花
萩は、その優雅な姿とは裏腹に、厳しい環境でも力強く育つ強い生命力を持っています。
この姿が、武士の潔さや忍耐強さと重なり、家紋にも多く使われました。
戦国武将の小早川隆景が、萩の家紋を用いていたことは有名な話ですね。
一見すると繊細な花が、武士の魂を象徴していたと思うと、さらに魅力的に感じられます。
今でも萩の花を家紋にしているご自宅も多いのではないでしょうか。よくわからない方も、蔵などに描かれている家紋をみてみると良いかもしれません。
実は「豆」をつける植物
萩はマメ科の植物です。
そのため、秋には蝶のような可愛らしい花が終わった後に、小さな豆のような実をつけます。
普段は花の美しさに目が行きがちですが、ぜひ実がなっている様子も観察してみてください。
マメ科の植物らしい、意外な一面を発見できるかもしれません。
月見と萩について
古来より、日本人は月を愛でる習慣を大切にしてきました。
その際に、ススキと共に欠かせない存在だったのが萩です。
「月に叢雲(むらくも)、花に風」という言葉があるように、月を見る際には萩を添えることで、秋の夜長の風情が一層高まりました。
月と萩は、日本の伝統的な美意識の中で、切っても切り離せない組み合わせなのです。
&YOUKAENでは秋の花を使用したフラワーアレンジメントを販売中!

&YOUKAENでは秋が旬のフラワーアレンジメントを販売中です。
この季節だけにしか出回らない旬のお花を使用して、女性にも男性のも贈れるようおしゃれに仕上げています。
状態の良いお花だけを使用して、クオリティの高いフラワーギフトを制作。フローリストが自信を持ってお出ししている商品です。
誕生日や結婚記念日、ご自宅用のインテリアにもおすすめ。ぜひ大切な方にプレゼントしてあげてくださいね。
お花は「季節をプレゼント」できる唯一のギフト。ぜひ、秋をお楽しみください。
秋の花を使ったおしゃれなフラワーアレンジメント
期間限定 和風フラワーアレンジメントM 「irodori」
¥8,250-
まとめ

萩は、「思案」や「内気」といった花言葉を持つ、奥ゆかしい花です。
秋の七草の一つとして、また『万葉集』に最も多く登場する花として、古くから日本人に愛されてきました。
萩を飾ることで、日本の豊かな歴史と文化を感じられることでしょう。
&YOUKAENでは秋にしか出回らないお花を使用して作る、おしゃれな花束やフラワーアレンジメントを販売しております。
どれもフローリストが丁寧に一つずつ制作しますので、大切な方へのプレゼントにおすすめ。
誕生日や結婚記念日に、&YOUKAENのフラワーギフトをお贈りください。
◆修正履歴
2025年12月9日:一部年号を修正。参考文献・出典情報を追記。
Aug 13, 2025