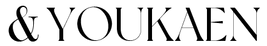ススキの花言葉って何? 歴史やトリビアについても紹介!

ススキの花言葉って何? 歴史やトリビアについても紹介!
秋の風に揺れる姿が美しいススキ。
お月見には欠かせない存在ですが、普段何気なく見ているこの植物に、奥深い花言葉や歴史が隠されていることをご存知でしょうか?
この記事では、ススキの基本情報から、意外と知られていない花言葉の意味と由来、そして古くから日本の文化に深く根付いてきたススキの歴史やトリビアまで、
お花屋さんの視点も交えながら丁寧に解説します。
ススキの新しい魅力を発見し、季節を楽しむヒントを見つけてください。
ススキとは?

ススキは、日本の秋の風景を代表する植物の一つです。その特徴や名前の由来など、基本情報を見ていきましょう。
ススキってどんな植物?
| 植物名 | ススキ(芒) |
| 学名 | Miscanthus sinensis |
| 科名 | イネ科 |
| 属名 | ススキ属 |
| 原産地 | 東アジア一帯 |
| 開花時期 | 8月~10月 |
ススキは、イネ科ススキ属に分類される多年草で、日本の秋の風物詩として親しまれています。
学名は「Miscanthus sinensis」といい、アジア東部を中心に広く分布しています。
茎はまっすぐに伸び、その先に特徴的なふわふわとした穂をつけます。
この穂が風になびく姿は非常に美しく、日本の四季の中でも特に秋の情緒を感じさせる植物として愛されています。
ススキはどんなところに生える?
ススキは、日本全国の山野や河川敷、日当たりの良い場所に自生しています。
特に、広々とした原っぱや土手などで群生している姿は、壮大な景観を作り出し、秋の風情を感じさせてくれます。
たくましい生命力を持つ植物で、一度根付くと丈夫に育ちます。
ススキのふわふわの部分は花?
ススキの穂は、一見すると綿毛のようにふわふわしていますが、実はこの部分こそがススキの花なんです。
厳密には、小さな花がたくさん集まって穂(かすい)を形成しています。
開花時期は9月〜10月頃で、最初は赤褐色を帯びていますが、成熟するにつれて白銀色に変化し、風になびく美しい姿を見せます。
ススキの名前の由来は?
ススキという名前の由来には諸説あります。代表的な説をいくつかご紹介しましょう。
・「すくすく伸びる」様子から「すす」と、草を意味する「き(木)」が組み合わさってできたという説。
・「洲々草(すずき)」が転じてススキになったという説。
・「芒(すすき)」という漢字は、音を表す「亡」と植物を表す「艹(くさかんむり)」から成り立っており、風になびく様子を表しているとも言われます。
秋の七草の一つ
ススキは、万葉集にも詠まれるなど、古くから親しまれてきた植物であり、秋の七草の一つに数えられています。
秋の七草は、ハギ、オバナ(ススキ)、クズ、ナデシコ、オミナエシ、フジバカマ、キキョウを指し、これらは平安時代に詠まれた歌に由来すると言われています。
ススキは「尾花(おばな)」とも呼ばれ、秋の風景には欠かせない存在として親しまれてきました。
ススキの花言葉は?

ススキには、そのたくましい姿や風になびく様子から生まれた、様々な花言葉があります。
ススキの花言葉には、「活力」「心が通じる」「雄々しい」「見栄え」「隠退」「なびく心」などがあります。
中にはポジティブな意味だけでなく、少しセンチメンタルな意味も含まれています。
ススキの花言葉の由来は?
それぞれの花言葉が持つ由来を見ていきましょう。
・「活力」「雄々しい」:どんな場所でも力強く育ち、生命力に満ちたススキの姿から来ています。
・「心が通じる」「なびく心」:風になびくススキの穂の様子が、互いの心が通じ合う様や、相手の意見に柔軟に従う様に例えられた説があります。
・「見栄え」:広大な野に群生したススキが作り出す壮大で美しい景観からきています。
・「隠退」:実りの秋を終え、枯れていくススキの様子を、第一線から退き隠居する姿に見立てた説です。
ススキは縁起の良い植物?
ススキは、古くから縁起物として扱われてきた植物です。特に、「魔除け」や「邪気払い」の効果があると言われています。
穂が稲穂に似ていることから、豊作の願いが込められたり、穂先が尖っていることから魔物を追い払う力があると信じられてきました。
そのため、魔除けとして家の軒先に飾られたり、お月見に供えられたりする文化が日本各地に根付いています。
ススキの歴史について

ススキは、日本の歴史や文化に深く関わってきました。その足跡をたどってみましょう。
万葉集にも登場するススキ
日本最古の歌集「万葉集」には、ススキが萩と並んで数多く詠まれています。
当時は「尾花(おばな)」という名前で親しまれ、秋の風景や人の心を表現する重要な存在でした。
例えば、「秋の野に 咲ける花をば 指折りかき数ふれば七草の花」といった歌に、ススキは秋の象徴として登場しています。
(参考元:万葉百科 奈良県立万葉文化館「秋の野に咲きたる花を指折りかき数ふれば七種の花」)
平安時代には「中秋の名月(十五夜)」に活躍
平安時代に中国から伝わったお月見の風習は、日本独自の文化として発展しました。
その中で、ススキはお供え物として定着していきました。稲穂の代わりに豊作を願う意味や、魔除けの意味が込められていたと考えられています。
また、風に揺れるススキの姿が風情があり、月を愛でる情緒に合致したことも、お月見に欠かせない存在となった理由の一つでしょう。
(参考元:あなゆかし「お月見の由来と歴史」)
茅葺き屋根の材料として
また、ススキは茅葺き屋根の主要な材料として大いに活用されていました。
耐久性や断熱性に優れ、庶民の生活に深く関わっていたことがわかります。
その丈夫さから、現在でも茅葺き屋根の修復にススキが使われることがあります。
(参考元:日本茅葺き文化協会「茅葺きとは」)
浮世絵や俳句にも登場するススキ
江戸時代の浮世絵や俳句にも、ススキは頻繁に描かれ、庶民にも身近な存在でした。
秋の風物詩として愛され、詩情を掻き立てるモチーフとなっていたのです。
松尾芭蕉の「名月や池をめぐりて夜もすがら」など、有名な俳句にも月とススキの組み合わせが登場し、日本の美意識と深く結びついています。
(参考元:Ukiyo-e Search「Rabbits in Bush Clover (Hagi) and Pampas Grass (Susuki)」)
(参考元:575筆まか勢「ススキ」)
ススキにまつわる文化や地域の伝承

ススキは、日本各地で様々な文化や伝承と結びついています。
「幽霊の正体見たり枯尾花」
これは有名なことわざですね。その意味は、「幽霊だと思っていたものの正体は、風に揺れる枯れたススキの穂だった」というものです。
暗闇で揺れるススキの穂が、不気味なものに見えた様を表しています。
このことわざは、思い込みや先入観に囚われず、物事の本質を見極める大切さを教える教訓としても使われます。
「中秋の名月(十五夜)」
ススキは単なる飾りではなく、お月見に欠かせない理由があります。
稲穂の代わりに豊作を願う意味や、魔除けの意味があることは前述した通りです。
さらに、月からの使者を迎える依り代(よりしろ)としての役割も持つとされています。
十五夜の飾り付けでは、お団子と一緒にススキを供えることで、豊穣への感謝と来年の豊作を願う気持ちを表します。
沖縄では魔除けとして使われる
地域によってススキの使われ方は様々です。
例えば、沖縄ではススキを魔除けとして家の軒先に飾る風習があります。
「鬼(マジムン)」と呼ばれる魔物が家に入らないよう結界としての役割を果たすと信じられています。
このように、ススキは日本各地で人々の暮らしや信仰に深く根付いてきた植物なのです。
ススキに関するトリビア

ススキにまつわる、ちょっとした面白い豆知識をご紹介します。
・猫じゃらし(エノコログサ)とススキは、見た目が似ているためよく間違われますが、実は異なる種類の植物です。ススキの方が穂が大きく、背丈も高くなります。
・花粉症の原因となるイネ科の植物の一つでもあります。秋に花粉症で悩む方は、ススキの花粉に注意が必要です。
・ススキの根は、生薬として利用されることがあります。漢方薬の一部に、解熱や利尿などの効果を持つ生薬として配合されることがあります。
・昔は、ススキの穂が、筆の材料としても使われたことがあると言われています。繊細な穂の形状が、筆の用途に適していたのでしょう。
&YOUKAENではススキをまとめて販売しています!

&YOUKAENでは秋の風情を楽しめるススキのギフトを販売しております。
ススキは、単体で飾るだけでも存在感があり、和風のインテリアやお月見の飾り付けに最適。
ススキは私たちフローリストが世田谷の市場から厳選して仕入れたものを使用します。
夜空の月が綺麗な季節に、ススキを飾って一年間の無病息災を願ってみてはいかがでしょうか?
秋の「ススキ」10本花束 高さ70cm
¥5,500-
ススキの出回り時期について
一般的に、ススキの出回り時期は8月下旬から10月頃までです。
中でも、最も美しい時期は中秋の名月の頃で、穂がふっくらと成熟し、白銀色に輝きます。
&YOUKAENでは新鮮で品質の良いススキを最適な時期に仕入れ、皆さまへお届けできるよう準備しております。
商品ページから販売期間や事前予約の有無をご確認いただけますので、ぜひチェックしてみてください。
まとめ

ススキは、私たちの身近にある植物でありながら、奥深い花言葉や豊かな歴史、そして多様な文化と深く結びついています。
風になびく穂の姿は、秋の訪れを感じさせ、私たちの心に安らぎと情緒を与えてくれます。
ススキの花言葉や背景を知ることで、今までとは異なる視点で季節の移ろいを感じられるでしょう。
&YOUKAENでは日本の美しい四季を彩る季節のお花を大切にしています。
ススキをはじめとする秋の花材も高品質なものを厳選し、皆さまのもとへお届けしています。
ご自宅のインテリアとして、大切な方への贈り物として、ススキを通して日本の美意識や季節の移ろいを感じてみませんか?
季節ごとのお花やギフトを多数ご用意し、皆さまのご来店を心よりお待ちしております。
◆修正履歴
2025年12月10日:一部年号を修正。参考文献・出典情報を追記。
Jul 29, 2025