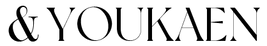お盆には何をして過ごす?風習やタブーについて紹介

お盆には何をして過ごす?風習やタブーについて紹介
お盆の時期が近づくと「一体何をすればいいの?」「どんな風習があるの?」と戸惑う方も多いかもしれません。
特に、伝統的な風習にあまり馴染みがない都市部の方にとっては、疑問に感じることも少なくないでしょう。お取引先様へのお盆の挨拶に困ってしまうこともしばしば…。
お盆は単なるお休み期間ではなく、ご先祖様が家に帰ってくる大切な時期であり、感謝の気持ちを伝えるための特別な行事がたくさんあります。
この記事では、お盆の基本的な意味から、期間中の主な風習ややること、そしてうっかり犯してしまいがちなタブーまで、詳しく解説します。
これを読めば、お盆の過ごし方や大切なマナーが分かり、心穏やかにご先祖様をお迎えできるはずです!
ぜひ最後までご覧ください。
まず、お盆とは?基本的な期間と種類

まず、お盆がどのような意味を持つのか、そしてその期間について解説します。
お盆は、ご先祖様の霊が子孫のもとへ帰ってくるとされている期間です。家族や親族が集まり、ご先祖様の供養を行う大切な日本の伝統行事です。
お盆の期間

お盆の期間は、地域によって大きく二つのパターンがあります
旧盆(月遅れ盆)
一般的に8月13日から16日を指します。全国的に最も広く行われているお盆の期間であり、多くの企業や学校がお盆休みを設けるのもこの時期です。
新盆(東京盆)
一部地域、特に東京では7月13日から16日にお盆を行う習慣があります。これは明治時代の改暦の際に、旧暦のお盆を新暦にそのまま当てはめた名残とされています。
どちらのお盆も行事の内容に大きな違いはありませんが、ご自身の地域や親族の習慣に合わせて期間を確認することが大切です。
新盆(初盆)と通常のお盆の違い

さて、ちょっとややこしいのですが、故人が亡くなってから四十九日の忌明け後に初めて迎えるお盆を「新盆(にいぼん/しんぼん)」、または「初盆(はつぼん)」と呼びます。
先ほどの東京盆のことを示す新盆と同じ字面なので混合される方がいらっしゃいますが、要注意です。
「初盆(新盆)」は通常のお盆と比べて、丁重に供養を行うのが一般的。
例えば、白い提灯(白提灯)を飾ったり、親族や故人と親しかった方を招いて法要を行ったりと、特別な準備をすることが多くあります。
故人を悼む気持ちをより深く表す時期とされています。
お盆の主な風習・やることリスト

お盆の期間中には、ご先祖様を迎え入れ、お見送りするための様々な風習や準備があります。
一つ一つ心を込めて行うことが、供養に繋がります。
詳しくみていきましょう。
お盆の準備(事前にすること)

お盆期間に入る前に、まずはご先祖様をお迎えするための準備を始めましょう!
お仏壇の掃除
ご先祖様をお迎えする前に、お仏壇を丁寧に清めましょう。埃を払い、仏具を磨くことで、清らかな気持ちでご先祖様をお迎えできます。
盆棚(精霊棚)の準備
お仏壇の前に、ご先祖様のための「盆棚(精霊棚)」を設けます。これはご先祖様が滞在する場所とされ、位牌やお供え物を飾ります。
飾り方
一般的には真菰(まこも)のござを敷き、その上に精霊馬、提灯、季節の野菜や果物、故人の好きだった食べ物などをお供えします。
お花(仏花)
盆棚やお仏壇を彩る「お供え花(仏花)」も大切な要素です。故人が安らかに過ごせるよう、心を込めて選びましょう。
精霊馬・精霊牛の作成
きゅうりとなすに割り箸などで脚をつけた「精霊馬(しょうりょううま)」と「精霊牛(しょうりょううし)」を用意します。
きゅうりの馬は「ご先祖様が早く家に帰ってこられるように」、なすの牛は「帰り道はゆっくりと景色を楽しみながら帰っていかれるように」という意味が込められています。
提灯(盆提灯)の準備
ご先祖様が迷わず家にたどり着けるように、盆提灯を飾ります。
白提灯
新盆(初盆)の家庭が用いるもので、故人の霊が初めて帰ってくる際の目印となります。お盆が終わったら燃やして供養するのが一般的です。
絵柄提灯
通常のお盆に用いる提灯で、毎年飾ることができます。
お供え物の準備
故人が好きだったものや、季節の果物、そうめん、だんごなどをお供えします。日持ちするものが喜ばれます。水やお茶を毎日替えることも忘れずに。
お盆期間中の過ごし方について

お盆の4日間は、ご先祖様と過ごすための特別な日です。
13日は「迎え盆(迎え火)」
ご先祖様の霊が自宅に帰ってくる日です。
夕方になったら、家の門口や庭先で「迎え火(むかえび)」を焚きます。
焙烙(ほうろく)と呼ばれる素焼きの皿の上で麻の茎(おがら)を燃やすのが一般的です。
マンションなど火が使えない場合は、提灯やLEDロウソクなどで代用することもあります。
14日・15日は「中日」
ご先祖様が自宅に滞在する期間です。
この間にお墓参りに行き、お墓を清めてお花やお供え物を供えます。
自宅ではお仏壇に手を合わせ、毎日お供え物を取り替えたり、線香をあげたりして供養します。親族が集まって会食をすることも多いでしょう。
16日は「送り盆(送り火)」
ご先祖様が浄土へ帰っていく日です。
迎え火と同様に、夕方に「送り火(おくりび)」を焚いて、ご先祖様を見送ります。
地域によっては、灯篭流しや精霊流しを行う場所もあります。
お寺への参拝
菩提寺がある場合は、お盆の期間中に寺院へ参拝し、お盆法要に参加することもあります。事前に日程を確認しておくとスムーズです。
現代でも同じように過ごすの?
あくまで上記に挙げた風習は伝統的なものですので、現代のライフスタイルに合わせて、全てをこなす必要はありません。
大切なのは、故人を偲び、感謝の気持ちを伝えること。できる範囲で心を込めて行うことが、何よりも重要です。
お盆の「これってタブー?」知っておきたい注意点

お盆にはいくつかのタブーや注意点があります。
これらも故人を敬う気持ちから生まれたものですが、現代では柔軟に考えられることも多いですので、参考までにとどめておいてください。
避けるべき行動・タブー

殺生(せっしょう)
お盆はご先祖様の魂が帰ってくる時期であり、殺生は避けるべきとされています。
釣りや虫取り、殺虫剤の使用などは控える方が良いとされています。
旅行・レジャー
お盆はご先祖様を迎え入れ、共に過ごす期間であるため、家を空けて旅行やレジャーに出かけることは好ましくないとされることがあります。
しかし、遠方への帰省や、やむを得ない事情がある場合は、お仏壇に一言断りを入れるなど、心を込めて供養すれば問題ないという考え方も広がっているのだとか。
結婚式などの慶事(けいじ)
お盆は仏事(弔事)であるため、結婚式やお祝い事などの慶事をこの期間に行うことは避けるべきとされています。
土いじり・草むしり
土の中にいる生き物を傷つける可能性があるため、お盆期間中の土いじりや畑仕事、草むしりなどは控えるべきだと言われています。
タブーに関するよくある質問

お盆に関してよく聞かれる疑問についても解説します。
Q: お盆に海や川に入ってはいけないって本当?
A:これは古くからの言い伝えで「お盆の時期はご先祖様の魂が水辺を通って帰ってくるため、その際に引き込まれる」といった迷信や、
精霊流しなど水に関する行事があるためとも言われます。
また、古くからこの時期は水難事故が増える傾向にあるため、安全を考慮してできた注意喚起とも考えられます。
そこまで気にしなくても大丈夫ですよ。注意して遊んでくださいね。
Q: お盆に髪を切ってはいけないって本当?
A: これも迷信です。
お盆に髪を切ること自体に直接的なタブーや悪い意味はありません。
昔からの習慣や言い伝えとして残っている地域もあるかもしれませんが、あまり気にする必要はないでしょう。
Q: お盆に引越しをしてもいい?
A: 仏事の期間に大きな行動を避けるという考え方から、引越しを避ける人も中にはいらっしゃいます。
しかし、これも絶対的なタブーというわけではありません。
大切なのは、引越しの前後でしっかりご先祖様へご挨拶し、新しい場所でも供養を続けることです。
これらのタブーや疑問に対する考え方は、地域や宗派、ご家庭によっても異なります。一番大切なのは、形式に囚われすぎず、故人を思う気持ちを大切にすることです。
まとめ

お盆は、ご先祖様をお迎えし、日頃の感謝の気持ちを伝えるための大切な期間です。
お盆の過ごし方や風習を知り、タブーとされることに配慮することで、より心穏やかにご先祖様と向き合うことができるでしょう。
お仏壇の掃除から盆棚の準備、迎え火や送り火、そしてお墓参りまで、様々なお盆の準備がありますが、
全てを完璧にこなすことよりも、故人を思う気持ちを込めてできる範囲で行うことが何よりも大切です。
お盆の準備を始めるにあたり、お仏壇を彩るお供え花も忘れてはならない大切な要素です。
心を込めて選んだお花は、ご先祖様への最高の贈り物となること間違いなし!
ぜひ一度、「&YOUKAEN」のお盆向けお供え花のラインナップをご覧ください。フローリストが花材からチョイスして作る手作りのフラワーギフトとなっておりますので、お盆に直接伺えない際の贈り物にもおすすめです。
Jun 25, 2025