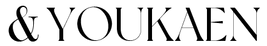しめ縄って何?| 日本文化の背景と由来から解説

しめ縄って何?| 日本文化の背景と由来から解説
お正月が近づくと、スーパーやデパート、そして街中の玄関先で「しめ縄」や「しめ飾り」を目にしますね。
毎年なんとなく飾っているかもしれませんが、これが単なる華やかな飾りではなく、日本の最も古い神話に由来する「神聖な結界」であることをご存知ですか?
「しめ縄」の本当の意味を知ることは、新年を迎える準備をより深く、丁寧なものにしてくれます。
この記事を読めば、「しめ縄の本当の意味」から、「なぜお正月に飾るのかという神話からの由来」、「正しい飾り方のルール(時期・場所)」まで、そのすべてがわかります。
最後には&YOUKAENのフローリストがデザインした現代のしめ縄飾りをご紹介。ぜひご覧くださいませ。
しめ縄とは?その基本的な意味

しめ縄ってどんな飾り?
しめ縄とは、収穫したばかりの「稲わら(新藁)」を編んで作られた縄に、「紙垂(しで)」と呼ばれるギザギザの白い紙を垂らした、神聖な縄のことです。
漢字では「注連縄」や「七五三縄」と書かれます。神社でご神木や拝殿に張られているのを見かける、あの縄と同じものです。
しめ縄が持つ3つの主要な役割
お正月に私たちが玄関に飾る「しめ縄(しめ飾り)」には、大きく分けて3つの重要な役割があります。
1. 神様を迎える清浄な場を示す(結界)
これが最大の役割です。
しめ縄の内側は「年神様(としがみさま)をお迎えするための、清められた神聖な場所(常世=とこよ)」であり、私たちが普段生活している外側の「俗世(常世=つねよ)」とを区別する「結界」の役割を果たします。
つまり、「我が家は年神様をお迎えする準備が整った、清浄な場所ですよ」というサインなのです。
2. 災厄や邪気を家に入れない(魔除け)
上記の結界機能と関連し、しめ縄は「魔除け・厄除け」の役割も持ちます。
神聖な場所を守るため、不浄なものや災厄(邪気)が家の中に入ってこないようにする「バリア」のような存在です。
3. 五穀豊穣・家内安全を願う(祈願)
しめ縄を飾り、年神様を丁重にお迎えし、おもてなしすることで、その年の「五穀豊穣」や「家内安全」「商売繁盛」を願う「祈りの象徴」でもあります。
しめ縄は何で作られている?
しめ縄の主な材料は「稲わら」です。
そして、多くのお正月飾りには、しめ縄以外にも様々な縁起物が組み合わされています。
・紙垂(しで): ギザギザの白い紙。雷や稲妻をかたどったものとされ、神様の降臨や清浄な場所を示します。
・裏白(うらじろ): シダ植物の一種。葉の裏が白いことから「心の潔白さ」や「白髪になるまでの長寿」を表します。
・ゆずり葉: 新しい葉が出ると古い葉が譲るように落ちるため「子孫繁栄」の象徴です。
・橙(だいだい): 実が木から落ちずに何代も残るため「家が代々栄える」という願いが込められています。
しめ縄の由来について

では、この「しめ縄」という文化は、一体いつ、どのようにして始まったのでしょうか。
そのルーツは、日本の神話と稲作信仰という、2つの深い源流にあります。
1. 天岩戸(あまのいわと)神話
しめ縄の神話的な起源は、『古事記』に記された日本で最も有名な神話の一つ「天岩戸隠れ」にあります。
1. 太陽神である天照大神(あまてらすおおみかみ)が、弟の素行の悪さに怒り、天岩戸という洞窟に隠れてしまいました。世界は闇に包まれます。
2. 困った八百万の神々は、岩戸の前で宴会を開き、天照大神の興味を引きます。
3. 天照大神が「何事か」と少しだけ岩戸を開けた瞬間、力の強い神(天手力男神)がぐっと岩戸を開け、天照大神を外に引きずり出しました。
4. そしてすかさず、別の神(布刀玉命)が、天照大神が二度と岩戸に戻れないよう、岩戸の入口に「しりくめ縄(=しめ縄の原型)」を張りました。
この神話こそが、しめ縄が「神聖な場所と俗世を分ける結界」であり、「一度入った神(良いもの)を逃さず、悪いものを入れない」という意味を持つようになった直接の由来なのです。
2. 稲作信仰とのつながり
神話と同時に、私たちの生活と深く結びついた由来もあります。なぜ、しめ縄の材料は「稲わら」なのでしょうか。
それは、古来より稲作を行ってきた日本人にとって、お米(稲)が単なる食料ではなく、神様が宿る神聖なものであり、一年の収穫(命の源)への感謝そのものだったからです。
新年に飾るしめ縄は、その年に収穫された新しい稲わら(新藁)で作るのが習わしです。
つまり、しめ縄は「収穫への感謝」と「翌年の豊作への祈り」が込められた、日本の稲作文化の象徴でもあるのです。
地域によって異なるしめ縄の形と特徴

「しめ縄」と一口に言っても、実は地域や神社によって様々な形や特徴があります。豆知識としていくつかご紹介します。
・左綯い(ひだりない)と右綯い(みぎない): 縄の編み方(綯い方)にも違いがあります。神様から見て左側(向かって右)を上位とするため、神聖な場所には「左綯い」が使われることが多いなど、様々な決まり事があります。
・牛蒡締め(ごぼうじめ): 片方が太く、もう片方が細くすぼまっていく、野菜の「牛蒡(ごぼう)」に似た形です。神棚などで最も一般的に見られる形で、太い方を神様(または上位)に向けて飾ります。
・出雲型(大根締め): 最も有名で迫力があるのが「出雲大社(いずもおおやしろ)」の巨大なしめ縄です。これは牛蒡締めとは逆に、真ん中が最も太く、両端が細くなる「大根締め」とも呼ばれる形です。
しめ縄はいつから飾る?(飾り方としきたりのルール)

「しめ縄」の神聖な意味がわかったところで、最も大切な実用的な知識、「いつからいつまで飾るのか」というルールを解説します。これは年神様をお迎えする上での大切なマナーです。
しめ縄を飾る時期(いつから?)
12月13日の「正月事始め」(お正月準備を始める日)以降なら、いつ飾っても構いません。
一般的には、クリスマス(25日)が過ぎた頃から大掃除を終えて飾り始めるご家庭が多いです。
飾るのにベストな日は「12月28日」と言われています。「八」が末広がりで縁起が良いためです。 遅くとも、30日までには飾るようにしましょう。
飾ってはいけない「NGな日」
逆に、飾るのを避けるべき日が2日間あります。
・12月29日: 「二重苦(にじゅうく)」または「苦(く)」に通じるため、縁起が悪い日とされています。この日に飾るのは避けましょう。
・12月31日: 大晦日に飾ることを「一夜飾り(いちやかざり)」と呼びます。これは、神様をお迎えするのに前日ギリギリに準備する「誠意のない行為」とされ、また「葬儀の準備(一夜限り)」を連想させるため、神様に対して非常に失礼にあたるとされています。
しめ縄を外す時期(いつまで?)
しめ縄は、「松の内(まつのうち)」(年神様がご家庭に滞在してくださる期間)が終わったら外します。 この「松の内」は地域によって異なり、
・関東地方:1月7日まで
・関西地方:1月15日(小正月)まで
とすることが多いです。ご自身の地域の慣習に従いましょう。
外したら「どんど焼き(左義長)」でお清め
外したしめ縄は、神聖なものですので、ゴミとして捨てるのは望ましくありません。
1月15日前後に、地域の神社などで行われる「どんど焼き(左義長)」と呼ばれる火祭りに持って行きましょう。
そこで他のお正月飾りと一緒に感謝を込めてお焚き上げし、煙と共に年神様を天にお送りするのが正式な作法です。
&YOUKAENではしめ縄飾りを販売中!

このように、しめ縄は日本の神話にまで遡る、非常に深く神聖な意味を持つ飾りです。
だからこそ、新年を迎える準備として、心を込めて選びたいものですね。
&YOUKAENでは、この伝統的な意味を大切にしながらも、現代の暮らしに合うようデザインされた、特別なしめ縄飾りをご用意しています。
瑞々しい新年を迎えるフレッシュなお正月飾り
私たちがお届けするしめ縄飾りは、伝統的な稲わらをベースに、お花屋さんならではの感性で、フレッシュ(生)の松(神様が宿る木)や、縁起の良い南天(難を転ずる)、稲穂(五穀豊穣)などをあしらいました。
年神様をお迎えするという伝統的な意味をしっかりと踏まえつつ、現代の住まいや玄関のドアにも美しく映える、モダンなデザインが特徴です。
プロのフローリストが一つひとつ心を込めてデザインした、高品質なしめ縄飾りで、清らかな新年をお迎えください。
【招福】瑞々しい干支飾り
¥7,700-
まとめ

「しめ縄」の本当の意味、ご理解いただけたでしょうか。
1.「しめ縄」とは、単なる飾りではなく、年神様をお迎えするために「神聖な場所と俗世を分ける結界」です。
2. その由来は、天照大神の「天岩戸」神話(二度と戻らないための結界)と、日本の「稲作信仰」(収穫への感謝)という2つの深いルーツを持ちます。
3. 飾る時期は「12月28日」が最適。縁起の悪い「29日(苦)」と、神様に失礼な「31日(一夜飾り)」は絶対に避けましょう。
しめ縄の本当の意味を知り、心を込めて準備することで、新しい年はきっと素晴らしいものになるはずです。
&YOUKAENがお届けする神聖で美しいしめ縄飾りで、晴れやかな新年をお迎えください。
Nov 04, 2025