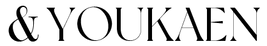榊ってなに?|歴史と文化的な役割を探る

日本の神社の神事や、家庭の神棚に供えられている緑の枝。それが榊(さかき)です。
一年中美しい緑を保つ榊は、私たち日本人にとって非常に身近でありながら、その歴史や文化的役割について深く知る機会は少ないかもしれません。
この記事では、神道において最も重要な神木とされる榊について、その由来や花言葉、そして日本の古代から現代に至るまでの役割を詳しく解説します。
榊の持つ意味を知ることは、日本の文化と精神性を理解することにつながります。また、神棚を正しく祀りたい方のために、実用的な情報もご紹介します。
榊とは?

まずは、神聖な植物とされる榊の基本的な情報を見ていきましょう
榊ってどんな植物?
| 植物名 | 榊 |
| 学名 |
Cleyera japonica |
| 科名 | モッコク科 |
| 属名 | サカキ属 |
| 原産地 | アジア |
榊は、モッコク科サカキ属に分類される常緑高木です。一年を通して葉を落とさず、濃い緑色を保つのが大きな特徴です。
葉は肉厚で光沢があり、縁にギザギザがない点(全縁)が、神棚に供えられる代用植物のヒサカキ(姫榊)と見分けるポイントの一つです。
日本では、神棚に供える神聖な神木として、古くから大切にされてきました。
榊はどこで育つ?
榊は、主に本州の中部以西から四国、九州、沖縄にかけての温暖な地域に自生する、日本固有の植物です。
特に温暖な気候を好むため、関東より北の地域では自生が少なく、代わりに近縁種のヒサカキ(姫榊)や他の常緑樹が榊の代用として使われることが多くなります。
榊の名前の由来について
榊という名前の由来には諸説ありますが、最も有力な説は以下の二つです。
・境の木(さかいのき)説: 神聖な領域(神様のいる世界)と人間が住む俗世との境界線を示す「境の木」を意味する「さかいき」が転じて「サカキ」となったという説。
・栄える木(さかえるき)説: 常に青々とした姿から、「栄える」ことを意味する「さかえるき」が転じたという説。
漢字の「榊」は、「木」と「神」を組み合わせた国字(日本で作られた漢字)であり、この一文字だけで神木であることを表しています。
榊の花言葉は?

榊の持つ花言葉は、その神聖な役割に由来する、力強く厳かなメッセージを持っています。
榊の花言葉「神を尊ぶ」「揺るがない」
これらの花言葉は、神への真摯な信仰心や、一年中変わらない緑の姿から来る不変の精神を象徴しています。
神棚に供える榊は、家庭の信仰心と、家族の平和や繁栄を願う心を映し出す存在と言えるでしょう。
榊の歴史的背景

榊が日本の文化、特に神道の祭祀において重要な役割を担うようになった歴史を探ります。
日本では古くから依代として考えられていた
日本では、自然界のあらゆるものに神が宿ると考えられてきました。
その中でも常緑樹は、「常緑で枯れにくい植物=神聖な力を宿す植物」と考えました。そのため古くから神事に使用されてきましたが、元々の「サカキ」という名称は常緑樹全般を指す言葉でした。
次第にサカキは「生命の象徴」とされ、神様が降りてくる目印や宿る場所、すなわち「依代(よりしろ)」として特別視されていきます。
祭祀を行う際には、榊を立てて神様を招き入れることが、古くから行われてきたとされています。(*現在のツバキ科(モッコク科)の特定の小高木を指す言葉へと限定されるのは後の話です)
(参考元:Wikipedia「Cleyera japonica」)
(参考元:國學院大学デジタルアーカイブ「sakaki」)
『古事記』『日本書紀』には榊の記述がある
榊は、日本の二大古典である『古事記』や『日本書紀』にも登場します。
仲哀天皇の条には「五百枝(いおえ)の賢木(さかき)」という表現があり、枝に勾玉、鏡、剣(三種の神器を模したもの)を掛けたと記されています。
また、景行天皇の条には「信(しつ)の山(現在の美濃地方などとされる)の榊」についての記述があります。
(参考元:國學院大学デジタルアーカイブ「sakaki」)
中世〜近世では家で榊を供える風習が確立
中世から近世にかけて、神棚を設けて神様を家庭で祀る風習が武家や庶民の間にも広まりました。奈良時代には「御斎所(みさいしょ)」と呼ばれる神聖な空間ができ、平安に入ると「神棚」と名前を変えました。徐々に貴族の家庭から武士の家庭へと広がっていき、江戸時代では庶民の生活にも浸透します。
これに伴い、神棚に榊を左右一対で供えるという習慣も定着し、現代の家庭での榊の文化へと繋がっています。
(参考元:弘前八幡宮(青森県) 公式サイト「神棚の起源と歴史」)
榊が持つ象徴的な意味

榊の葉や姿は、神聖な意味を持っています。
美しい緑は永遠の生命
榊が一年中青々とした葉を保つ常緑樹であることは、「永遠の生命」や「不老長寿」を象徴します。
神に供えることで、家族の繁栄と、永遠に変わらない希望を願う意味が込められています。
神と人の世界を分ける木
名前の由来にもある通り、榊は神の領域と人の領域を区切る結界の役割を持っています。
神棚に供えることで、そこが神聖な場所であることを示しているのです。
葉の艶は神の光の象徴
榊の葉が持つ独特の濃い緑色と、瑞々しい艶(つや)は、神の光や神の威光を映し出すと考えられてきました。
この葉の艶を保つことが、神様を大切に祀る心に繋がります。
榊の文化について

榊は、神道におけるさまざまな祭祀具や儀式に用いられます。
神木としての榊、神籬(ひもろぎ)
神籬(ひもろぎ)とは、臨時に祭祀を行う場所を設ける際に、中央に榊を立て、周囲を注連縄(しめなわ)で囲んで神聖な場所とするものです。
この榊が、神様が降臨する依代の役割を果たします。
玉串(たまぐし)について
玉串(たまぐし)は、榊の枝に紙垂(しで)と呼ばれる白い紙を付けたもので、神事の際に神様に捧げるものです。
玉串奉奠(たまぐしほうてん)という儀式で、参拝者がこれを捧げる行為は、神と人をつなぐ役割を持つ、最も重要な作法の一つです。
祓串(はらえぐし)について
祓串(はらえぐし)は、神主が祭祀の際に、参列者やお供え物に対して振り、お祓いをするために用いる道具です。
これも榊の枝や木に麻や紙を付けたもので、穢れを祓い清める力があるとされています。
家庭(神棚)での榊の文化

家庭の神棚に榊を供えることは、神様への敬意を示す基本的な作法です。
神棚での榊の飾り方
榊は、神棚の左右に置かれた榊立てに、一対(二束)で供えます。葉の先端が神棚の正面(外側)を向くように飾るのが基本です。
水は毎日取り替え、常に瑞々しい緑を保つように心がけることが、神様への礼儀とされています。
1日15日(朔日と月半ば)に取り替える
神棚の榊は、毎月1日(朔日)と15日(月半ば)の月に二回、新鮮なものに交換するのが古くからの慣習です。
これは、神様に毎月月初と月半ばにご挨拶を申し上げるという信仰心から来ています。
たとえ枯れていなくても、この日を目安に新しい榊に取り替えることで、常に神棚を清浄に保つことができます。
&YOUKAENではヒサカキ(姫榊)のサブスプリクションを販売中

榊を常に瑞々しく保ちたいけれど、毎月買いに行くのが大変だという方も多いのではないでしょうか。
&YOUKAENでは、新鮮なヒサカキ(姫榊)を定期的にお届けするサブスクリプションサービスをご用意しております。
月に2回届く!簡単ヒサカキのサブスク
お花のプロが選んだ榊(ヒサカキ)を毎月2回お届けいたします。
届いた榊をお手持ちの花瓶に入れるだけでOK。そのまま神棚にお飾りいただけます。
定期配送で決められた日に確実にお手元に届きますので、近くにお花屋さんのない方や買いに行く時間がない方におすすめです。
本商品は定期便で確約いただいておりますので、送料を無料にて配送いたします。
【毎月2回自宅にお届け】榊の定期便 ヒサカキサブスク 日本の伝統を受け継ぐ定期便
¥1,980-
榊とヒサカキの違いについて
市場で流通している神棚用の枝には、榊(本榊)とヒサカキ(姫榊)の二種類があります。
・榊(本榊):モッコク科サカキ属。葉は大きく肉厚。縁がギザギザしていないのが特徴。温暖な西日本で多く流通。
・ヒサカキ(姫榊):モッコク科ヒサカキ属。葉はやや小さく細長い。縁に細かいギザギザがあるのが特徴。寒さに強く、東日本で広く流通。
ヒサカキは、榊が生育しにくい寒冷地での代用として用いられてきましたが、現在では榊と同様に神棚に供えるものとして広く認知され、全国的に流通しています。
&YOUKAENのサブスクリプションで、手軽に神棚の榊を新鮮に保ちましょう。
まとめ

榊は、単なる植物ではなく、日本の神道文化において「神と人の境」を示す依代であり、「永遠の生命」を象徴する神木です。
その歴史は神話の時代にまで遡り、現代の神棚の文化にまで深く根付いています。榊を供えることは、日本の伝統を大切にし、家族の平和と繁栄を願う心を表すことです。
毎月1日と15日には、ぜひ榊(ヒサカキ)を新しくし、清々しい気持ちで神様をお迎えください。新鮮なヒサカキのサブスクリプションは、&YOUKAENから簡単にお申し込みいただけます。
◆修正履歴
2025年12月9日:一部年号を修正。参考文献・出典情報を追記。
Oct 14, 2025