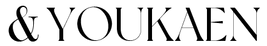重陽の節句とは?由来と歴史を詳しく解説

重陽の節句とは?由来と歴史を詳しく解説
秋の深まりを感じさせる9月9日。
この日が「重陽の節句」、または「菊の節句」と呼ばれる日であることをご存知でしょうか。
菊を飾ったり、菊酒を飲んだりして不老長寿を願う、古くから伝わる日本の美しい風習です。
しかし、他の節句に比べてあまり馴染みがないという方もいらっしゃるかもしれません。
この記事では、重陽の節句の由来や歴史、現代における過ごし方、そして長寿の象徴である菊の魅力について、お花屋さんの視点も交えながら詳しく解説します。
この機会に重陽の節句について知ることで、秋の暮らしをより一層豊かにしてみませんか?
重陽の節句とは何か

まずは、重陽の節句がどんな行事なのか、その基本的な意味を見ていきましょう。
重陽の節句ってなに?
重陽の節句とは、旧暦の9月9日にあたる節句のことです。
五節句の最後を飾る節句で、菊が見頃を迎える時期であることから「菊の節句」とも呼ばれます。
この日は長寿や無病息災を願う日とされており、菊を飾ったり、菊酒を飲んだりして、秋の訪れを祝います。
五節句の中での位置づけは?
五節句とは、季節の節目を祝い、邪気を払うために行われた行事で、人日(じんじつ、1月7日)、上巳(じょうし、3月3日)、端午(たんご、5月5日)、七夕(しちせき、7月7日)、そして重陽(ちょうよう、9月9日)の五つを指します。
重陽の節句は、この五節句の中で唯一、国民の祝日ではありません。
しかし、縁起の良いとされる奇数の最大の数字「九」が重なる日であり、最もめでたい日とされていました。
名称の由来は?
重陽の節句の名称は、古代中国の「陰陽思想(いんようしそう)」に由来します。
・陰陽思想では、奇数を「陽(よう)」の数、偶数を「陰(いん)」の数としました。
・この中で陽の数が一番大きい「九」が重なる日であることから、「重陽」と呼ばれるようになりました。
また、「菊の節句」と呼ばれる理由は、菊が咲き誇る季節であることに加え、邪気を払う力があるとされ、長寿を象徴する花だったからです。
古代中国から渡った風習
重陽の節句の起源は、古代中国の不老長寿を願う民間信仰にあるとされています。
この風習が日本に伝わり、独自の文化と結びついて発展していきました。
こちらに関しては次の章で詳しく解説してみましょう。
重陽の節句の歴史的背景

重陽の節句は、古代中国で生まれ、時代を経て日本に伝わり、独自の文化と融合しながら発展してきました。
その歴史を紐解くことで、なぜこの日が大切にされてきたのかが見えてきます。
重陽の節句の起源は古代中国の民間信仰

重陽の節句の起源は紀元前まで遡り、古代中国の不老長寿を願う民間信仰にあるとされています。
中国の陰陽思想では、9月9日は陽の最大の数である「九」が重なる日であり、非常に縁起の良い日とされました。
しかし、陽が極まると陰に転じるという思想もあり、この日に災いが起こることを恐れる風習も生まれました。
そのため、人々は厄払いのために菊を飾ったり、高い場所に登ったりして、長寿と無病息災を願いました。
菊は古くから邪気を払う力を持つ神聖な花とされており、その効能にあやかったのです。
奈良時代に日本に伝来、平安時代に宮中で華開く

重陽の節句は、奈良時代に遣唐使によって日本に伝わったとされています。
当時の日本は、中国の文化を積極的に取り入れており、五節句もその一つでした。
特に、平安時代になると、重陽の節句は宮中行事として盛大に行われるようになりました。
貴族たちは、菊が咲き誇る庭で詩歌を詠み、菊を愛でる「観菊の宴(かんぎくのえん)」を催しました。
この宴では、菊の美しさを楽しみながら、長寿を願いました。
また、この時代に生まれたのが「菊の被綿(きせわた)」という雅な風習です。
9月8日の夜、宮中の女官たちが菊の花に真綿を被せ、夜露を染み込ませました。
翌朝、菊の香りと露を吸い込んだその綿で体を清めることで、若さや長寿を保てると信じられていたのです。
この風習は、当時の貴族たちの優雅な暮らしぶりを物語っています。
江戸時代に庶民の行事として普及

重陽の節句が広く庶民に広まったのは江戸時代です。
五代将軍徳川綱吉の時代に、五節句が公式な祝日として定められました。
これにより、重陽の節句は庶民の間でも重要な行事となり、菊を飾ったり、菊酒を飲んだりして、長寿や無病息災を願う風習が定着しました。
この時代には、栗の旬と重なることから「栗の節句」とも呼ばれるようになりました。
人々は、秋の豊かな収穫への感謝を込めて、栗ご飯や栗を使った料理を家族で囲みました。
武家では菊の飾りや菊の御紋にちなんだ家紋を用いて、尚武の精神を養う風習もありました。
現代に受け継がれる「菊の文化」

明治時代に入り、太陽暦が導入されると、重陽の節句は他の節句に比べて徐々に馴染みが薄くなりました。
しかし、長寿や健康を願うという根本的な意味合いは現代にも受け継がれています。
菊は皇室の御紋としても使われるなど、日本を象徴する花としてその文化的価値を保ち続けています。
現在でも、全国各地で菊まつりや菊花展が開催され、人々は様々な種類の菊を楽しんでいます。
重陽の節句は忘れられつつある行事かもしれませんが、菊を愛でるという文化は今も私たちの暮らしに生きているのです。
重陽の節句に関連する伝統行事

重陽の節句にまつわる伝統行事がいくつかあります。その背景を知ることでより深く楽しめますよ。ぜひ真似してみてくださいね。
菊酒を飲む習慣がある!
「菊酒」とは、菊の花を浸した酒を飲む風習です。
菊の香りが移った菊酒を飲むことで、邪気を払い、不老長寿を得られると信じられていました。
ただし、現代の観賞用の菊は食用ではないため、専門の食用菊を使うか、香りを楽しむ程度にとどめるようにしましょう。
栗や秋の味覚を楽しむ!
重陽の節句は、栗の旬にあたるため「栗の節句」とも呼ばれます。
重陽の節句の夕飯には、栗ご飯や栗きんとんなど、栗を使った料理を楽しむ習慣があります。
秋の収穫への感謝と結びついていた、日本らしい風習です。
重陽の節句に行われる祭りやイベント
全国各地では、重陽の節句に合わせて菊を使った祭り(菊まつりなど)が開催されます。
また、皇室でも菊花の着綿(きくかのきせわた)などの伝統行事が行われており、その歴史が今も生きていることを示しています。
重陽の節句にまつわる神話や伝説

重陽の節句に欠かせない菊は、単なる美しい花ではありません。
その背景には、古代中国から伝わる不老不死の思想や神話が深く関わっています。
ここでは、菊がなぜ長寿の象徴とされてきたのか、その神秘的な物語をご紹介します。
菊と仙人、そして不老不死の霊薬

重陽の節句と菊の関係を語る上で、唐代の道教の教えは欠かせません。
道教とは、不老不死や現世での幸福を追求する中国の民間信仰であり、菊はその思想と強く結びついていました。
人々は、仙人が菊の露を飲んで長寿を保ったという伝説を信じていました。
一つの有名な伝説に、以下のような物語があります。
『昔、河南省にある茱萸(しゅゆ)という山に、一人の仙人が住んでいました。その仙人は、山に自生する菊の花についた夜露を集めて飲んでいたところ、いつしか不老長寿の体を手に入れたそうです。その仙人が住んでいた山の麓には菊が群生しており、その露が川に流れ込んでいたため、その川の水を飲んでいた村人たちも皆長生きしたと伝えられています』
この伝説から、「菊には邪気を払い、不老不死の力がある」と信じられるようになりました。
そのため、重陽の節句には菊の露を浴びたり、菊を浸した酒を飲んだりする風習が生まれたのです。
中国の詩に詠まれた菊と長寿

重陽の節句に菊が重要な役割を担うのは、不老長寿の象徴としてだけでなく、高潔さや孤高の美を表す花としても認識されていたからです。
唐代の詩人、陶淵明(とうえんめい)は、菊を愛することで知られており、その詩には菊が度々登場します。
「東籬(とうり)の下に菊を采(と)る、悠然として南山を見る」
この有名な一節は、俗世間から離れ、自然の中で悠々自適に暮らす様を表しています。
このように、菊は道教の思想と結びつき、俗世の煩悩から解き放たれた、清らかな精神の象徴としても捉えられていました。
不老不死とは、単に肉体的な命が続くことだけでなく、精神的な高潔さを保ち続けることも意味していたのです。
重陽の節句に込められた「九」の力

重陽の節句が9月9日であることも、神話や伝説と深く関わっています。
古代中国の陰陽思想では、奇数は「陽」の数、偶数は「陰」の数とされますが、陽の数は極まると陰に転じるという思想がありました。
九は陽の最大の数であり、これが二つ重なる重陽の日は、最もめでたいと同時に、最も不安定な日と考えられていました。
そのため、人々はこの日に高い場所に登り、邪気を払う力を持つとされる茱萸(しゅゆ)を身につけ、菊酒を飲むことで、災いを避けていました。
また、この日は菊の精霊が咲き誇る特別な日とされ、菊を飾り、菊にまつわる儀式を行うことで、その強い生命力と邪気を払う力を授かろうとしたのです。
これらの神話や伝説は、現代の私たちにとっても、重陽の節句をより深く味わうための物語として、心に響くものです。
菊を愛でることは、単なる観賞だけでなく、古の人々が抱いた長寿や健康への願い、そして清らかな精神への憧れに触れることなのです。
現代における重陽の節句の過ごし方

伝統的な風習を現代のライフスタイルに合わせて楽しむ方法をご紹介します。
無病息災を家族で祈ろう
重陽の節句を改めて知ることで、9月9日を家族で集まり、互いの健康や長寿を願う日とするのはいかがでしょうか。
特にご高齢のご家族がいらっしゃる場合は、敬老の日(9月第3月曜日)と合わせて長寿をお祝いする良い機会にもなります。
夕飯に「栗ご飯」を食べよう
旬の味覚を楽しむことも、節句を感じる良い方法です。夕飯に栗を使った栗ご飯を囲んで、秋の訪れを感じてみましょう。
秋茄子を食べるのもGood!
重陽の節句の時期は、秋茄子も美味しい季節です。
「秋茄子は嫁に食わすな」ということわざは、美味しいから嫁に食べさせたくないという意味と、体を冷やすから嫁に食べさせないという意味があります。
旬の茄子を楽しむことも、秋の風情を感じる良い方法です。
菊を使ったフラワーアレンジメント・花束を飾ろう!

重陽の節句の象徴である菊を飾ることは、最も手軽で美しい過ごし方です。
現代では、ポンポンのように丸く可愛らしい「マム」や、スプレー状に咲く「スプレーマム」といった洋菊も豊富にあります。
伝統的な和菊と洋菊を組み合わせると、モダンなアレンジメントも楽しめます。
菊が持つ「高貴」「長寿」といった花言葉を考えながら、お花を飾る楽しみを味わってみてはいかがでしょうか。
重陽の節句におすすめの花束(敬老の日にもおすすめ!)
秋のお花を使った 洋風のSpecial花束 「秋の粧い」
¥15,950-
菊を使ったフラワーアレンジメント・花束を飾ろう!

私たち&YOUKAENでは、重陽の節句にぴったりな菊を豊富に取り揃えております。
伝統的な和菊から、ポップでモダンな洋菊(マム、スプレーマム)まで、多様な品種をご用意しています。
菊を中心としたアレンジメントや花束は、ご自宅の飾りとしてだけでなく、ご高齢のご両親やお世話になった方への長寿を願うギフトとしても最適です。
敬老の日にもプレゼントできるギフトをご用意しておりますので、ぜひご検討くださいませ。
重陽の節句におすすめのフラワーアレンジメント(敬老の日にもおすすめ!)
和風フラワーアレンジメントS 「kaki」
¥6,050-
まとめ

重陽の節句は、あまり知られていないかもしれませんが、長寿や健康を願う、日本人にとって大切な伝統文化です。
菊を飾り、栗や秋の味覚を楽しむことで、心豊かなひとときを過ごせるでしょう。
&YOUKAENでは皆さまが重陽の節句を楽しくお過ごしいただけるよう、高品質な菊をはじめ、秋の季節を彩る様々なお花をご用意しております。
専門フローリストが、皆さまのお花選びを心を込めてサポートさせていただきます。
Aug 04, 2025