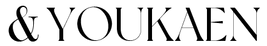お正月に欠かせない門松の歴史と意味

お正月に欠かせない門松の歴史と意味
お正月に家の門や玄関に飾られる「門松」。 誰もが知っているお正月飾りの象徴ですが、なぜ飾るのか、その深い意味や歴史をご存知ですか?
門松は、お正月に各家庭へやってくる「とても大切な神様」をお迎えするための、重要な目印です。
この記事では、「門松」の本当の意味から、使われる植物(松竹梅)に込められた縁起、正しい飾り時期、そして意外と知らない歴史や地域による違いまで、門松のすべてを植物を扱うプロのフローリストの視点で詳しく解説します。
どうして門松を正月に飾るの?

お正月に門松を飾るのには、古くから伝わる大切な理由があります。それは、新年の神様をお迎えする「おもてなし」の心そのものです。
門松は歳神様(年神様)が降りてくる「目印」
「門松」に関する最大の疑問は、「何のために飾るの?」ということでしょう。
門松の最大の役割は、新年に私たちに健康や五穀豊穣など、その年の幸福をもたらすためにやってくる「歳神様(年神様)」が、迷わずに家へ来てくださるための「目印(ランドマーク)」です。
同時に、年神様が訪れた際に宿る「依り代(よりしろ)」としての役割も持っています。 つまり、お正月に門松を立てるという行為は、「年神様、我が家へようこそ!ここでお待ちしております」という、歓迎のサインなのです。
門松の構成
門松は、一般的に「松」「竹」「梅」という、3つの縁起の良い植物で構成されています(地域によっては梅が葉牡丹などに変わることもあります)。
なぜこの3つが選ばれたのかというと、それは、それぞれが非常に縁起の良い、おめでたい意味を持つ植物だからです。
次の章で詳しく解説していきましょう。
門松に込められた意味と象徴

ここが、私たちお花屋さんが最も大切にしている部分です。
「松竹梅(しょうちくばい)」と呼ばれるこの3つの植物が、なぜこれほどまでにおめでたいとされるのか、その理由を解説します。
松は「長寿」を表す
松は、厳しい冬でも青々とした葉を保つ常緑樹です。その生命力の強さから、古くから「不老長寿」の象徴とされてきました。
また、「祀る(まつる)」にも通じることから、神様が宿る木として神聖視されてきた植物でもあります。
竹は「成長と繁栄」を表す
竹は、驚くべきスピードで天に向かってまっすぐに伸びていきます。その姿から、「成長」「繁栄」「生命力」の象徴とされています。
また、雪の重みにも折れずに耐え、節目がはっきりしていることから、「誠実さ」や「潔白さ」も表す、非常に縁起の良い植物です。
梅は「忍耐と生命力」を表す
梅は、まだ寒い冬の終わりに、他のどの花よりも早く美しい花を咲かせます。
その姿から、厳しい冬を耐え抜く「忍耐」と、春を告げる「生命力」「開運」「気高さ」の象徴とされています。
門松では松と竹が主体となり、梅は彩りとして添えられることが多いですが、松竹梅は日本で最高のおめでたい組み合わせとされています。
門松を飾る時期は?

門松は神様をお迎えする大切なものですから、飾る時期にもルールがあります。
「門松はいつからいつまで飾るのか」という、正しい知識を身につけておきましょう。
12月28日までに飾るのがGood!
門松を飾り始めるのは、12月13日の「正月事始め」以降であればいつでも構いません。
一般的には、クリスマス(25日)が終わり、大掃除を済ませた26日頃から飾り始めます。
特に「12月28日」は、「八」が末広がりで縁起が良いため、この日に飾るのがベストとされています。遅くとも30日までには飾り終えましょう。
29日と31日はNG
逆に、飾るのを避けるべき日が2日間あります。
・12月29日: 「二重苦(にじゅうく)」や「苦(く)松(待つ)」につながるとされ、縁起が悪い日とされています。
・12月31日: 大晦日に飾ることを「一夜飾り」と呼びます。これはお葬式の準備と同じ(一夜限り)で、慌ただしく準備することが年神様に対して失礼にあたるとされています。
松の内まで飾る
門松を飾っておく期間を「松の内(まつのうち)」と呼びます。これは、年神様がご家庭に滞在してくださる期間を指します。
この期間は地域によって異なりますが、一般的に
・関東:1月7日まで
・関西:1月15日(小正月)まで
とすることが多いです。松の内が終わったら、感謝を込めて片付け、神社のお焚き上げ(どんど焼きなど)で納めるのが丁寧な方法です。
門松の歴史について

「門松」は、いつ頃から今のような形になったのでしょうか。その歴史をたどると、日本の文化の変遷が見えてきます。
歳神様を迎える依り代(よりしろ)から始まった
門松の起源は非常に古く、人々が家の前に常緑樹(特に神聖視されていた松)を立て、それを目印(依り代)として年神様をお迎えしていたシンプルな風習から始まったとされています。
(参考元:政府広報「Highlighting Japan」)
奈良〜平安時代に宮中儀式として登場
奈良・平安時代になると、中国から伝わった文化と融合し、宮中の正月行事として「松」を引き抜き、飾る儀式(小松引き)が登場しました。この時点ではまだ竹は組み合わされていなかったようです。
(参考元:富山県薬剤師会「富薬 No.378」)
鎌倉〜室町時代に形が定着し庶民へ広がる
鎌倉時代に武家社会にもお正月の風習が広まり、室町時代には現在のように「松」と「竹」をセットで飾るスタイルが定着したと言われています。この頃から庶民の間にも広まっていきました。
(参考元:WorldAtlas「What is Kadomatsu?」)
江戸時代には現代の形へ発展
江戸時代に入ると、庶民の文化が花開き、正月行事もさらに発展します。
現在私たちが見るような、松竹梅をあしらった豪華な門松や、竹の切り方(そぎ・寸胴)にこだわったデザインが登場しました。
(参考書籍:『日本風俗史事典』(11907419) p.116-117「門松」)
現代ではミニ門松や玄関飾りとして一般家庭に
現代では、都市部を中心に大きな門松を立てる家は少なくなりました。
しかし、その「年神様をお迎えする」という大切な意味合いは受け継がれ、「ミニ門松」や、松や竹を使った「お正月飾り(リースやアレンジメント)」として、今も一般家庭の玄関を華やかに飾っています。
門松は地域ごとに特徴がある

門松は全国一律ではなく、地域によってデザインに特徴があることをご存知でしょうか。特に分かりやすいのが「竹の切り口」です。
関東
関東(特に江戸)では、竹を斜めに切る「そぎ」が主流です。
これは武家文化の影響が強く、徳川家康が「(敵を)斬る」という威勢の良さや「笑っているように見える」形を好んだという説があります。(諸説あり)
関西
関西(特に京)では、竹の節目で真横に切る「寸胴(ずんどう)」が主流です。
これは公家文化の影響とも言われ、切り口(節)を見せることから「笑い竹」と呼ばれ、福を呼び込むとされています。
九州
九州地方では、竹が非常に長かったり、藁(わら)を豪華に使ったりと、さらに多様な形の門松が見られます。
まとめ

「門松」について、その深い意味や歴史をご理解いただけたでしょうか。
1.「門松」は、新年の幸福をもたらす「年神様」を歓迎し、お迎えするための大切な「目印」です。
2.門松を構成する「松(長寿)」「竹(繁栄)」「梅(生命力)」は、日本で最高のおめでたい植物の組み合わせです。
3.飾る時期は「12月28日まで」に飾り付け、片付けるのは「松の内(1月7日または15日)」が終わってからが基本です。
大きな門松を立てるのは現代の住環境では難しいかもしれません。 しかし、その根底にある「年神様をお迎えし、おもてなしする」という清々しい心は、今も昔も変わらず大切にしたい日本の伝統です。
&YOUKAENでは、門松を立てるのが難しいご家庭でも、気軽に年神様をお迎えできるよう、門松に使われる「松」や「梅」、そして「難を転ずる」とされる「南天」といった縁起の良い植物を使った、現代の住まいにも飾りやすいお正月用のアレンジメントやブーケを多数ご用意しています。
門松と同じように、年神様をお迎えする「依り代」として、プロのフローリストが心を込めてデザインした華やかなお花を、玄関やリビングに飾ってみませんか?
◆修正履歴
2025年12月9日:一部年号について、根拠の確認状況に合わせて表現を修正。参考文献・出典情報を追記。
Oct 29, 2025