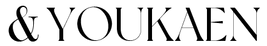月見団子の意味を知って、お月見を楽しもう!

月見団子の意味を知って、お月見を楽しもう!
秋の訪れを告げる「十五夜」。その象徴ともいえる「月見団子」は、私たちの食卓を彩るだけでなく、古くから様々な願いが込められた特別なお供え物です。
毎年何気なく飾っている方も多いかもしれませんが、その一つ一つに奥深い意味があることをご存知でしょうか?
この記事では、月見団子の意味や歴史、正しい飾り方から、月にまつわる楽しい神話まで、お花屋さんの視点も交えながら徹底的に解説します。
月見団子の深い意味を知り、今年のお月見をもっと心豊かなひとときにしてください。
月見団子とは?

月見団子は、お月見に欠かせない存在ですが、その役割や歴史を知ることで、お月見をより深く楽しめます。
月見団子の基本的な役割は?
月見団子は、十五夜に月へお供えする団子のことです。
その役割は単なるお菓子ではありません。その年の収穫への感謝と、来年の豊作を祈願する意味合いが込められています。
また、丸い形が満月を象徴しており、家族の円満や健康、幸福を願う意味も持ちます。
神様と人を繋ぐ「依り代(よりしろ)」としての役割も果たし、月からの恵みを受けるための大切な供物と考えられています。
月見団子の歴史は?
お月見の風習は、平安時代に中国から伝来し、当初は貴族の間で広まりました。
その頃は、月へのお供え物として、餅や旬の芋などが供えられていたようです。
現在の月見団子が一般に普及したのは、江戸時代に入ってからです。
農耕社会だった当時の日本では、米の収穫に感謝する意味で、米粉を使った団子がお供え物として定着していきました。
月見団子は「十五夜」だけに飾るの?
月見団子は基本的に「十五夜(中秋の名月)」に飾りますが、お月見は十五夜だけではありません。
旧暦9月13日の「十三夜(後の月)」や、旧暦10月10日の「十日夜(とおかんや)」にも飾る習慣があります。
・十三夜は「栗名月」や「豆名月」とも呼ばれ、栗や豆を供えることが多いです。十五夜に見逃した方でも、十三夜でお月見を楽しめます。
・十日夜は十五夜や十三夜とは異なり、収穫祭の意味合いが特に強いとされています。
十五夜と十三夜の両方をお月見することを「二夜の月」と呼び、縁起が良いとされています。
月見団子と里芋の関係について
十五夜は「芋名月(いもめいげつ)」とも呼ばれることがあります。
これは、里芋が古くから日本の主要な作物であり、十五夜の時期に収穫期を迎えるため、感謝の気持ちを込めて月に供えられたためです。
地域によっては、月見団子の形が里芋に似ているものを作る習慣も残っています。
月見団子は何個飾る?
月見団子の個数には、十五夜の月にちなんだ意味が込められています。
・基本は十五夜なので15個飾ります。
・十三夜の場合は13個、十日夜の場合は10個という地域もあります。
積み方はピラミッド型に積むのが一般的です。例えば15個の場合、一番下に9個、その上に4個、一番上に2個を積みます。
積み上げる理由は、高くして月に感謝の気持ちを伝えるためや、豊穣を願う意味が込められているのだとされています。
月見団子と一緒に飾るものは?

月見団子だけでなく、様々なアイテムを一緒に飾ることで、お月見の雰囲気をより一層引き立てられます。
お月様からみて左側に「ススキ」
お月見に欠かせない存在、それがススキです。
ススキは稲穂に似ていることから豊作を願う意味が込められており、鋭い穂先は魔除けの効果を持つと信じられています。
また、月からの使者を迎える依り代としての役割も果たすため、お月見には必須のアイテムです。
飾り方のコツとしては、月を正面に見て左側にススキを飾るのが一般的な配置です。
美しく新鮮なススキを飾ることで、お月見のしつらえがぐっと高まり、清々しい空間を演出できます。
おすすめのススキ商品
秋の「ススキ」10本花束 高さ70cm
¥5,500-
季節の果物と一緒に飾る
秋の旬の果物も、月へのお供え物として最適です。
柿、ぶどう、梨など、その季節に採れる新鮮な果物を供えることで、収穫への感謝を表し、季節の恵みを享受する意味があります。
彩り豊かに飾ることで、お月見の雰囲気がより一層華やかになるでしょう。
三方(さんぼう)に置いて飾ると上級者!
より丁寧にお月見を楽しみたい方には、三方を使うのがおすすめです。
三方とは、神事でお供え物を載せる台のことで、これに月見団子を載せることで、神様への敬意を表すことができます。
伝統的なお月見の雰囲気を演出し、特別なひとときを過ごせるでしょう。
基本的には床の間に飾りましょう
お月見のお供え物は、月のよく見える床の間に飾るのが最も良いとされています。
床の間は家の中でも神聖な場所とされており、月への感謝を捧げるにふさわしい空間です。
床の間がない場合は月が出ている方の窓側に飾りましょう
マンションや現代の住宅では床の間がないことも多いですが、心配ありません。お月見はどんな場所でも楽しめます。
月がよく見える窓際やベランダに、テーブルや棚の上に清めたスペースを作り、お月見のしつらえを整えましょう。
大切なのは月を愛でる気持ちです。
月見団子にまつわる神話と伝説

月見団子には、古くから伝わる楽しい神話や伝説が深く関わっています。これらを知ることで、お月見の物語性をより深く感じられます。
月の表面でうさぎが餅つきをしているように見える!
日本のお月見の定番といえば、月の表面に見える模様を「うさぎが餅つきをしている」とワイワイキャッキャとすることですよね。
この視覚的な認識は、後述する仏教説話に由来し、うさぎが月に昇って餅つきをしている姿に見立てられたものです。
月見団子が丸い形をしているのも、この餅つきを連想させるためであると言われています。
帝釈天とうさぎについて
「月のうさぎ」の物語は、仏教の「ジャータカ物語」に登場する逸話がもとになっています。
ある日、帝釈天(たいしゃくてん)が老僧に姿を変えて現れ、飢えていると動物たちに食べ物を求めました。
猿は木の実を、狐は魚を集めましたが、うさぎだけは何も持っておらず、自ら火の中に飛び込み、身を焼いて老僧に捧げようとしたのです。
帝釈天はそのうさぎの慈悲の心に深く感動し、その崇高な行いを永遠に語り継ぐため、うさぎを月に昇らせたと伝えられています。
うさぎを象った月見団子を飾ってもGood!
近年では、伝統的な丸い団子だけでなく、可愛らしいうさぎの形をした月見団子も人気を集めています。
スーパーや和菓子屋さんで見かけることも増えましたね。うさぎ団子を飾ることで、子供たちにも「月のうさぎ」の物語を伝えやすく、お月見をより楽しむきっかけになります。
伝統を大切にしつつ、現代の楽しみ方も取り入れるのは素敵なことですね。
まとめ

月見団子は、単なるお菓子ではありません。
豊作への感謝、家族の幸福、そして月に宿る神秘的な力への敬意が込められた大切なお供え物です。
その意味や由来、正しい飾り方を知ることで、毎年のお月見はより一層深い感動を与えてくれるでしょう。
月を見上げ、月見団子を囲むひとときは、私たちの心を癒し、季節の移ろいを感じさせてくれます。
&YOUKAENでは皆さまのお月見がより豊かになるよう、お月見に欠かせないススキをはじめ、秋の季節を彩る様々なお花をご用意しております。
秋の花を使用しておしゃれな花束やおしゃれなフラワーアレンジメントを制作。花材はフローリストが目で見て選んだ高品質なお花を使用。
月見団子とススキ、秋のお花を飾り、満月の下で心豊かなお月見をお過ごしください。
Jul 31, 2025